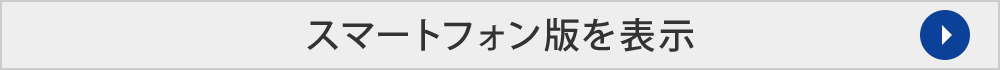里親制度
里親制度とは?
保護者がいない、または、さまざまな事情で保護者と離れて暮らさなければならない子どもを、家族の一員として自らの家庭に迎え入れ、保護者に代わり温かい愛情と家庭的な雰囲気で育ててくださる方を「里親」と言います。里親制度は児童福祉法に基づく「子どもの福祉」のための制度です。

(参照:長崎県里親育成センターすくすく)
現在、さまざまな事情で保護者と離れて暮らさなければならない子どもは全国に約42,000人、長崎県に約450人以上おり、里親家庭や児童養護施設等で元気に暮らしていますが、里親の担い手はまだまだ十分ではありません。
そこで、長崎県では里親になってくださる方を募集しています。少しでも子どもが豊かに育つ地域社会をつくることが出来ればと考えています。
里親の種類とは?
里親には次の4種類があります。
養育里親
要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当な児童)を、その状況が解消するまで、一時的、あるいは子どもが自立するまで養育する里親。
専門里親
特に支援が必要な児童(虐待による心身の影響が大きい、非行などの問題を抱えている、身体・知的・精神の障がいがあるなど)を養育する里親。
養子縁組里親
養子縁組を前提に要保護児童を養育する里親。
親族里親
民法に定める扶養義務者(3親等以内の親族)及びその配偶者である親族が要保護児童を養育する里親。
里親委託の役割とは?
- 次のような効果が期待できることから、社会的養護では里親委託を優先して検討。
(a) 特定の大人との愛着関係の下で養育され、安心感の中で自己肯定感を育み、基本的信頼感を獲得できる
(b) 適切な家庭生活を体験する中で、家族のありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルにできる
(c) 家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学び、地域社会の中で社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得できる - 里親は、委託解除後も関係を持ち、いわば実家的な役割を持つことができる。
- 養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4つの類型の特色を生かしながら推進。
里親になるための要件とは?
里親になるために、特別な資格は必要ありません。心身共に健康で子どもの養育に理解と熱意、そして愛情がある方であれば、どなたでも申込みができます。ただし、研修の受講などの条件を満たし、知事から里親として認定・登録されることが必要です。
里親の支援について
相談体制
各里親には、専門的な知識を有する相談員が担当につき、訪問や電話による相談を随時受け付けています。
養育費
子どもを委託された里親には、毎月里親手当や生活費、教育費等の委託費が公費から支給されます。
(例)養育里親として中学生1名を委託された場合
- 里親手当:90,000円/月
- 生活費:52,620円/月
- 教育費:4,380円/月
- 部活動費、学習塾費、給食費、医療費等:実費分支給等
(単価は令和4年度時点)
※里親手当とは、里親に対する報酬ではなく、児童等に直接必要な諸経費の為に支給されるものです。
※養子縁組里親及び親族里親には、生活費や教育費等は支給されますが、里親手当は支給されません。
研修
定期的に開催される養育技術に関する研修に無料で参加できます。
長崎県里親会
里親同士のつながりを図るために、県内の里親で構成された長崎県里親会主催の里親・里子交流会やサロンに参加できます。
里親出前講座のお知らせ
里親制度の説明や長崎県内で実際に里親をされている方の体験談等、約1時間程度の里親出前講座を県内各市町で実施しています。事前の申込は不要で、参加費は無料ですので、お気軽にご参加ください。
※令和5年度は9月13日(水曜日)14時~15時に西海保健センター(西海市西海町木場郷2235番地)にて実施しました。
里親体験談

里親ストーリー(PNG:496.2KB) (参照:こども家庭庁)
子どもが健やかに成長するには、家族に愛され、また子ども自身が愛されていることを実感することが大切です。日本にはさまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもが約42,000人います。里親制度とは、そうした子どもたちを自分の家庭に迎え、家族の”あたたかさ”に触れる機会を提供する制度です。
実際に里親をされた方や里親家庭で育った方の体験談を載せておりますので、ぜひご覧ください。
お問い合わせ先
| 長崎県里親育成センターすくすく (長崎県委託事業) |
長崎県大村市 西大村本町127-3 |
0957-53-7343 |
| 長崎こども・女性・障害者支援センター | 長崎県長崎市 橋口町10-22 |
095-844-6166 |
| 佐世保こども・女性・障害者支援センター | 長崎県佐世保市 万徳町10-3 |
0956-24-5080 |