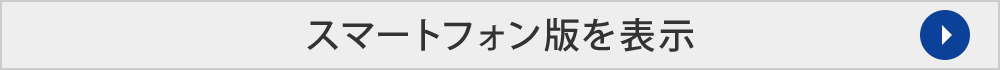お知らせ&よくある質問
お知らせ
土砂災害特別警戒区域に指定された土地の固定資産税評価について
土砂災害防止法に基づき、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)として危険区域に指定された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に制限などが発生することから、西海市では、その影響を考慮して令和7年度から固定資産税評価額を減額補正します。
(補正区分)
宅地
宅地比準雑種地
(補正率)
対象の土地の固定資産税評価額に補正率を適用して減額します。補正率はその土地の総面積のうちにレッドゾーン指定された面積が占める割合(面積割合)に応じて以下のとおりとなります。
| 面積割合 | 補正率 |
| 25%未満 | 0.9 |
| 25%以上50%未満 | 0.8 |
| 50%以上 | 0.7 |
固定資産税のよくある質問についてお答えします
問1
固定資産の評価替えとはどのようなものですか?
答1
土地と家屋の評価は、3年毎に総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、資産の価額を決定します。令和6年度は評価替えの基準年度となり、この評価額は、原則として3年間据え置かれますが、基準年度以外でも土地の区画・形質の変更や地目の変更などがあった土地や新増築があった家屋は改めて評価されます。
また、土地は、地価が下落傾向にある場合は、基準年度以外でも評価額を修正する場合もあります。地価が上昇又は横ばいの傾向にある地域は、評価額の修正は行われません。
問2
評価替えしたのに家屋の評価額が下がらないのはどうしてですか?
答2
再建築価格が上昇したためです。
家屋の評価額は、次の1.×2.×3.×4.の計算方法で求めます。
1.再建築価格
2.損耗の状況による減点補正率
3.受給事情による減点補正率
4.評点一点当たりの価額
令和6年度は、評価替えの基準年度ですが、近年の資材費等の高騰の影響により再建築価格が上昇しています。しかし、再建築価格の影響により評価額が上昇した場合は、据置きになります。
また、経年減点補正率が下がりきっている場合も評価額は据置きとなります。家屋の評価額は必ずしも評価年度ごとに下がることにはなりません。
問3
Aさんは、今年3月1日に土地・建物をBさんに売り、所有権移転登記も同日付で済ませましたが、今年度の固定資産税はどちらが納めるのですか?
答3
固定資産税は、地方税法により1月1日(賦課期日)現在で土地については土地登記簿または土地補充台帳に、家屋については建物登記簿または家屋補充台帳に所有者として登記または登録されている方が納税義務者となります。したがって、今年度まではAさんが納めることになります。
問4
固定資産税の納税義務者が死亡したときは?
答4
以後の納税については、死亡された納税義務者の相続人のうちどなたかに代表者となっていただく必要がありますので、税務課へ『相続人代表者指定(変更)届及び固定資産現所有者申告書』の届出が必要です。
この相続人代表者指定(変更)届及び固定資産現所有者申告書は、課税の便宜を図るために届けるものであり、登記の名義人は法務局で相続登記を行わないと変更されません。
問5
相続登記の義務化が始まったのはいつからですか?
答5
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まっています。登記の手続きは法務局で行いますので、詳しくは、法務局にお尋ねください。
問6
家を新築、取り壊したときなどは、届出が必要ですか?
答6
家を新築や増・改築したとき、または、家を取り壊したときは、税務課への届出が必要です。
家を取り壊したとき届出がなされていない場合には、固定資産税が課税されたままになる事もありますのでご注意ください。
問7
令和3年に住宅を新築したのですが、令和7年度分から急に固定資産税が高くなりました。なぜですか?
答7
新築住宅は、固定資産税(新築家屋分)の減額措置が3年間適用されますが、この減額措置が切れて、令和7年度から軽減前の本来の税額に戻ったためです。なお、長期優良住宅の減額措置は5年間です。
問8
私は、昨年住宅を壊しましたが、土地については、今年から税額が急に高くなっています。なぜですか?
答8
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税(土地分)が減額されています。したがって、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると住宅の固定資産税はかからなくなりますが、特例の適用がなくなるため、土地の固定資産税額が高くなります。
問9
いらなくなった土地を市で引き取ってもらえますか?
答9
市で引き取ったり寄付を受けることはありません。
公共工事などで必要になった場合は個別に相談することはありますが、それ以外で寄付などを受け付けることはありません。