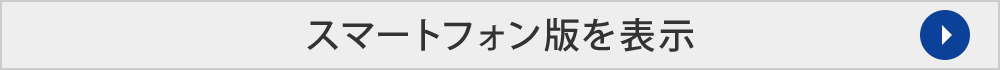国民年金
国民年金(市民課・総合支所市民課) |
加入する方
|
20歳から60歳になるまで40年間、原則として誰もが国民年金に加入しなければなりません。
この間、私たちのライフステージには、成人、就職、退職、自営、結婚などさまざまな節目があります。
3種類ある国民年金の加入の仕方も、その節目によって変わり、そのつど手続きが必要です。
|
第1号被保険者
|
農林漁業、自営業者などの方とその配偶者、学生、フリーター、家事手伝いなどの方。
加入手続きは、市役所市民課または総合支所で行い、保険料は日本年金機構から送られてくる納付書で納めるか、口座振替で納めます。 |
第2号被保険者
|
| 厚生年金保険・共済組合に加入している方。加入手続きや保険料納付などは会社などが行ってくれますので、自分で行う必要はありません。 |
第3号被保険者
|
第2号被保険者に扶養されている配偶者。自分で保険料を納める必要はありませんが、扶養している第2号被保険者が所属する事業所で届出が必要です。
|
手続きが必要なとき
|
つぎのような場合には、手続きが必要です。
自営業の方とその配偶者、学生、フリーターなど
次の方は手続きが必要です
| こんなとき |
被保険者の種別 |
届出場所 |
| 学生や会社などに勤めていない方が20歳になったとき |
第1号被保険者 |
市役所 |
| 60歳になる前に就職して厚生年金保険に加入したとき |
第1号被保険者
→第2号被保険者
|
事業所 |
| 配偶者が就職し、サラリーマンの被扶養者となったとき |
第1号被保険者
→第3号被保険者
|
事業所 |
| 海外へ転出し、引き続き加入するとき |
第1号被保険者
→任意加入被保険者
|
市役所 |
|
|
厚生年金保険に加入の方
|
次の方は手続きが必要です
| こんなとき |
被保険者の種別 |
届出場所 |
| 20歳になる前に就職して厚生年金保険に加入したとき |
第2号被保険者 |
事業所 |
| 60歳になる前に、会社などを退職したとき |
第2号被保険者
→第1号被保険者
|
市役所 |
| 勤めをやめて、自営業者の被扶養配偶者となったとき |
第2号被保険者
→第1号被保険者
|
市役所 |
| 勤めをやめて、サラリーマンの被扶養配偶者となったとき |
第2号被保険者
→第3号被保険者
|
事業所 |
|
|
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方
|
次の方は手続きが必要です
| こんなとき |
被保険者の種別 |
届出場所 |
| 配偶者が退職し、被扶養配偶者でなくなったとき |
第3号被保険者
→第1号被保険者
|
市役所 |
| 収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき |
第3号被保険者
→第1号被保険者
|
市役所 |
| 60歳になる前に就職して厚生年金保険に加入したとき |
第3号被保険者
→第2号被保険者
|
事業所 |
|
|
保険料免除申請
|
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下のため、保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除されます。免除の種類は全額免除、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(2分の1納付)、4分の1免除(4分の3納付)があり、免除された期間は資格期間として計算されますが、受給年金額は保険料を定額納付した場合と比較し、全額免除は3分の1、4分の1納付は2分の1、2分の1納付は3分の2、4分の3納付は6分の5となります。なお、免除された期間は、10年間前までさかのぼって、保険料を追納することができます。
参考:保険料の免除制度について(日本年金機構ホームページ)
|
学生納付特例制度
|
学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料を後払いできます。
特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
なお、特例を受けた期間は、10年前までさかのぼって、保険料を追納することができます。
参考:学生納付特例制度(日本年金機構ホームページ)
|
若年者納付猶予制度
|
低所得である若年者(20歳代)が、将来の無年金、低年金となることを防止するために、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により、保険料の納付を猶予するものです。猶予された期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。なお、猶予された期間は10年間前までさかのぼって保険料を追納することができます。
参考:若年者納付猶予制度(日本年金機構ホームページ)
|
年金の種類
|
年金の種類は以下のとおりです
| 種類 |
内容 |
| 老齢基礎年金 |
25年以上保険料を納めた方(保険料免除期間含む)に65歳から支給。
希望すれば60歳から受けられますが、年金額は減額されます。 |
| 障害基礎年金 |
国民年金加入中に、初診日がある病気やけがで障害者になった場合に支給。20歳前の障害によって障害者になった場合は20歳から支給。この場合、本人の所得による支給制限あり。 |
| 遺族基礎年金 |
国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた遺族(子のある妻又は子)に支給。死亡した方が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要。 |
| 寡婦年金 |
第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給。 |
| 付加年金 |
第1号被保険者として付加保険料を納めた方に老齢基礎年金と合わせて支給。 |
| 死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡したときその遺族に支給。 |
| 特別障害給付金 |
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について福祉的措置として支給。 |
|
|
国民年金って何?(日本年金機構からのお知らせ)
|
国民年金基金って何?(長崎県国民年金基金ホームページ)
|