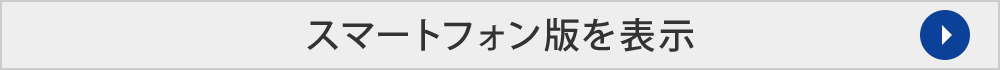償却資産
固定資産税の概要
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
- 納税義務者 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者
- 税率 1.4÷100(1.4%)
償却資産の概要
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
R8償却資産申告書手引き (Wordファイル: 363.5KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (Excelファイル: 39.5KB)
種類別明細書(減少) (Excelファイル: 35.5KB)
マイナンバーについて(チラシ) (Wordファイル: 455.9KB)
償却資産の具体例
法人や、個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートを貸し付けている方、農業や漁業を営んでいる方が、その事業のために用いている構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などの有形固定資産が課税されます。 ただし、家庭用の資産や販売用に陳列保管している商品などは含みません。 また、鉱業権・漁業権のような無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車、または軽自動車税の課税対象となっている軽自動車等は、課税の対象とはなりません。 なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸付ける場合も含みます。
・構築物
門扉、広告塔、舗装路面、緑化設備、外構、受変電設備、自家発電機、ビニールハウスなど
・機械及び装置
工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、耕耘機などの農機具(小型特殊自動車を除く)、太陽光発電設備など
・船舶
モーターボート、客船、漁船など
・航空機
旅客機、ヘリコプター、飛行船など
・車輌・運搬具
大型特殊自動車、貨車、客車など(自動車税、軽自動車税の対象となるものを除く)
・工具・器具・備品
各種工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機、パソコン、ルームエアコンなど
償却資産の税額等の算出方法
(1)償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。
ア、前年中に取得した資産(取得月に関わらず半年分を償却します。)
取得価格 × (1-耐用年数に応ずる減価率×1/2)または下表のA = 評価額 イ、前年前に取得した資産 前年度の評価額 × (1-耐用年数に応ずる減価率)または下表のB = 評価額
| 耐用年数 | 耐用年数 に応ずる 減価率 r | 減価残存率 | |
| 前年中取得 1年目 A | 前年前取得 2年目以降 B | ||
| 2 | 0.684 | 0.658 | 0.316 |
| 3 | 0.536 | 0.732 | 0.464 |
この表に関するお問合せは、税務課資産税班へお願いします。
(注)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。
(2)課税標準額は、各資産の評価額を合算した額(決定価格/1,000円未満切り捨て)となります。また、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。
(注)課税標準額の合算額が150万円未満の場合は、課税されません。
(3)税額の計算方法は、課税標準額(千円未満切捨て)×税率(1.4%)=税額(百円未満切捨て)
詳しい計算方法は、税務課資産税班にお問い合わせください。
減価残存率表(68KB) (PDFファイル: 68.4KB)
太陽光発電設備の取り扱いについて
太陽光発電設備を遊休地や事業用家屋の屋根等に設置した場合、または住宅用家屋であっても10kW以上の発電設備等は、事業用資産として固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。
ただし、家屋として固定資産税の課税対象となっている建材型ソーラーパネルについては、申告の必要はありません。また、一定の要件を満たす設備には、下記のとおり課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
課税標準の特例を適用するには「固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る申請書」に加えて、各種関係書類が必要です。
課税標準の特例申請書(37KB) (Excelファイル: 37.5KB)
| 特例対象資産 | 取得時期 | 特例率 | 適用条項 | 添付書類 |
| 内航船舶 | なし | 2分の1 | 地方税法第349条の3 第5項 | ・船舶原簿、船籍票および登録票の写し 等 |
| 特定再生可能エネルギー発電設備 |
令和2年4月1日~令和6年3月31日 |
1,000キロワット未満→3分の2 1,000キロワット以上→4分の3 |
地方税法附則第15条 第26項 |
・一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し ・経済産業省が発行した、再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者(九州電力株式会社)と契約している契約書の写し ・設備に関する経費の内訳(見積書・領収書等工事費(取得価格)の内訳のわかるもの) ・参考となる図面等 |
この表に関するお問合せは、税務課資産税班へお願いします。
従来、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていました。しかし、平成28年4月1日取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が、特例の対象となります。
生産性向上特別措置法による償却資産の標準課税の特例について
生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画については、こちらをご覧ください。
農耕作業用トレーラをお持ちの方へ
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、農耕作業用トレーラは小型特殊自動車の取り扱いとなりました。
それに伴い、これまで償却資産として申告されていたトレーラも、原則として軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
個人番号の本人確認について
平成28年1月から、償却資産申告書にマイナンバーを記載するようになっています。
西海市が本人からマイナンバーの提供を受ける場合(本人がマイナンバーを記載した申告書を提出する場合)には、正しい個人番号であることの確認(番号確認)と、個人番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)の2つの確認を行うことが必要になります。
マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、次のものを忘れずにご提示ください。
|
番号確認 |
身元確認 |
|
1、個人番号カード (注)市町村に申請し交付された、マイナンバーを記載した顔写真付のカード 2、個人番号が記載された住民票(写し) |
1つで確認できるもの 個人番号カード・運転免許証・住基カード(写真付)・パスポート・身体障害者手帳など 2つで確認できるもの 健康保険証・住基カード(写真なし)・介護保険証・年金手帳・原爆手帳その他氏名・生年月日・住所などが記載されたもの |
償却資産の申告制度と調査について
償却資産を所有しておられる方は、毎年1月1日現在における資産の状況を、1月31日までにその資産が所在する市町村に申告していただく義務があります。
申告の必要な資産をお持ちの方で、申告書が届かない場合は、税務課資産税班にご連絡ください。
また、税務課では、固定資産税(償却資産)の申告書などをもとに、地方税法に基づき調査を実施しています。この調査は、事業用資産の所有者の方を対象に減価償却明細書または固定資産台帳などを拝見させていただき、申告内容との照合や確認を行うものです。
事前にご連絡の上、直接、事業所を訪問させていただくか、関係書類の提出をお願いする等の方法により実施させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
なお、調査の結果、申告内容を訂正する必要がある場合は、調査年度を含めて、5年間分について遡及しますので、あらかじめご了承ください。
インターネットによる電子申告の受付について
インターネットによる電子申告も受け付けています。詳しくは、eLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。http://www.eltax.jp/